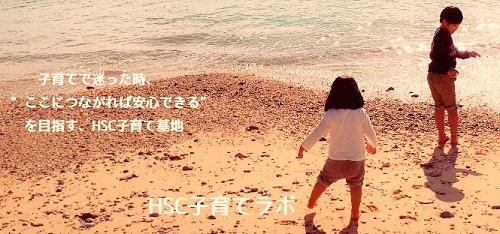ーポッドキャスト「コルクラボの温度」での対談、配信のお知らせー
妻である心理カウンセラー“Kokokaku”と息子“たける”とともに、
5月23日(水)、ポッドキャスト「コルクラボの温度」の収録に行って参りました。
収録は、東京・渋谷にある株式会社コルクさんの会議室で行われました。
株式会社コルクさんとは、あの『君たちはどう生きるか』『宇宙兄弟』『ドラゴン桜』を仕掛け、メガヒット編集者である 佐渡島 庸平(さどしま ようへい)さんが設立された、クリエイターのエージェントを行う会社です。
対談は、ライターでポッドキャスターのとっちーさんのナビゲートで、Dr.ゆうすけさん、Kokokaku、そして私の4名+たけるで行われました。
Dr.ゆうすけさんは、メンタルヘルスや “自己肯定感” がライフワークという内科のお医者さんで、メンタルヘルスや自己肯定感に関することをツイートやnoteなどで発信していらっしゃいます。
主に、HSC(Highly Sensitive Child)やメンタルヘルスについてお話させてもらってきました。
20分×2本、前編(今回)と後編(次回)に分けての配信です。
ご清聴頂けたら幸いです
【HSCの基礎知識と子育て】
日本での歴史が浅く、まだ認知度の低いHSC
HSC(Highly Sensitive Child)とは、生まれつき『とても敏感な“子ども”』のことで、
『とても敏感な“人”』のことはHSP(Highly Sensitive Person)と言い、いずれもアメリカの心理学者、エレイン・N・アーロン博士によって提唱された概念です。
その歴史を紐解くと、アーロン博士によって、高い敏感性に関するたくさんの調査と研究が重ねられ、1996年にまずアメリカで『The Highly Sensitive Person』というタイトルで出版されました。そして、この本は大ベストセラーになり、その後世界各国で翻訳出版されています。
日本では、2000年に『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』(富田香里訳/講談社)というタイトルで翻訳出版(現在、SB文庫より刊行)されて以来、HSPという言葉は、徐々に知られるようになってはいます。
一方で、HSCという言葉はそれより大幅に遅く、すでに2002年にはアーロン博士によって『The Highly Sensitive Child』というタイトルでHSCについて詳しく書かれた本が出版されていたものの、日本語に翻訳され、『ひといちばい敏感な子』(明橋大二訳/1万年堂出版)として日本で出版されたのが2015年と、まだ年数も浅いので認知度も低いようです。
また認知度が低い要因として、HSC(HSP)自体は、障がいや病名ではなく、あくまでも心理学的な概念なので、医療関係者における認知度がまだ高くないというのも、理由の一つと思われます。
HSCの割合は?
アーロン博士によると、子ども全体の15~20%(ほぼ5人に1人)が「生まれつき敏感なHSC」であることがわかっているとしています。
HSCは大人になったら必ずHSPになる?
Highly Sensitive、つまり「とても敏感」というのは “気質”のこと。
“気質”というのは、生まれつき備わった性質のことです。
身内との関係や育つ環境・社会環境に適応していくために、様々な要素を取り入れながら、後天的にその多くがつくられていく「性格」とは違って、
生まれ持った“気質”=Highly Sensitive(高い敏感性)は、本質的には大人になっても変わることはありません。
「生きづらさ」や「自己否定感」を抱えやすいHSC
子どもにはそれぞれ個性や独自性が存在し、それぞれに得手・不得手があります。
中でもHSCは、細かいことに気がつき、過剰に刺激や情報を受け止めるため、疲れやすく、慎重で状況をよく観察してから行動します。
自分のペースで思索・行動することを好み、監視されたり、評価されたり、押しつけられたりすることを嫌います。
また、人の集まる場所や騒がしいところが苦手で、新しいことや初対面の人と関わることを躊躇したり、慣れた環境や状況が変わるのを嫌がったりする傾向が見られます。
このようなHSCの生得的な気質である、
「小さなことを気にする自分」「ちょっとしたことに敏感に反応する自分」
「なかなか決断ができない、行動を起こすのに時間がかかる自分」を、
もっとも大切な人から肯定的に受け止めてもらえるか否かで、自分の気質をポジティブに捉えていくか、ネガティブに捉えていくかということについての影響は大きいでしょう。
HSCの場合は、親御さんや周りの大人の人たちがその子の気質の特性を知って、気質に合わせた育て方を行っていくか否か、さらには、その子とともに、気質に合った生き方(教育や職業など)の選択を行っていくか否かは、その子にとっての、その後の「生きやすさ」、「生きづらさ」にまで影響を及ぼしていくものと考えられるのです。
またHSCは、集団に合わせることよりも、自分のペースで行動することを好んだり、ほかの子は問題なくできることを躊躇したり、小さなことを気にしたりしがちですので、
親御さんは「もっと強い子に育ってほしい」「早く社会に適応してほしい」という思いから、苦手なことを克服させなければならないと考えてしまったりします。
そのため、
外向性を基準とする多数派の考え方・感じ方を強要してしまったり、
「あの子はできるのに、あなたはどうしてできないの?」
「そんな細かいこと気にしないの!」「クヨクヨ考えすぎ!」
「イライラさせないで!」「そんなことだと世の中渡っていけないよ!」
などの言葉で、気づかないうちに、子どもの気質を否定してしまったり、心に傷を負わせてしまったりすることで、「自己否定感」や「トラウマ」を抱えた多くのHSCに影響が出ているというのが実際のようです。
HSCと学校
多くの学校は、外向型の子どもたち向けにつくられているため、HSCの中には、様々な不利を強いられて、不適応を起こしやすかったりする子がいます。
その、不適応を起こしやすい理由として、HSCに多い16の特徴を挙げてみました。
【HSCに多い、学校に適応しにくい16の特徴】
③ 外向型の子どもたち向けにつくられている学校で、求められることを苦手に感じることが多く、人と比較したり、うまくいかなかったりした場合に自信を失いがちです。
④ 人の集まる場所や騒がしいところが苦手です。誰かの大声や、誰かが怒鳴る声を耳にしたり、誰かが叱られているシーンを目にしたりするだけでつらいと言います。
⑤ 1対1で話をするのを好みます。大勢の前でスピーチをすることや、大勢の人と会話をすることが苦手な傾向にあります。
⑥ 親友がクラスの中に1人でもいると安心ですが、クラス替えで親友と離れなければならなくなったりすると、すごく落ち込んだりします。
⑦ 物事を始めたり、人の輪に加わったりするなど、行動を起こすのにも時間がかかります。
これは目の前の状況をじっくりと観察し、情報を深く処理(大丈夫かどうか確認)してから行動するためです。
⑧ 刺激を受けすぎて、それに圧倒されると、落ち着きがなくなったり、話を聞けなくなったり、物事がうまくできなかったりします。恥ずかしさや刺激が多すぎて不安を感じる状況や環境では、冷静さや自制心を失って、その子が持っている本来の良さや力が発揮できなくなるのです。
⑨ 想定外のことや突発的な出来事に対してパニックになってしまうことがあります。
⑩ 自分と他人との間を隔てる「境界」が薄いことが多く、他人のネガティブな気持ちや感情の影響を受けやすい傾向にあります。例えば、他人の気分に影響されて、動揺したり、悲しくなって元気がなくなったりするなど。
⑪ 安心できていない人に、急に話しかけられたり、頭をなでられたり、顔や体を触られたり、抱きつかれたりすることを嫌がります。
⑫ 嫌だと思っても、なかなか「No」が言えません。支配的な人や、あなたのためになると言って受け入れさせるような関わり方をしてくる人には特に、です。
⑬ 先生がどのような人かの影響は大きいです。相性が良くない場合は、地獄だと言います。
⑭ 子ども扱いにする人や権威を示す人、権力をふりかざす人が極端に苦手です。
⑮ 自分の気質に合わないことに対して、ストレス反応(様々な形での行動や症状としての反応…HSCの場合「落ち着きがなくなる」「固まる」「泣きやすい」「駄々をこねる」「言葉遣いや態度が乱暴になる」「すぐにカッとなる」「ものに当たる」「引きこもる」、「不眠」「発熱」「頭痛」「吐き気」「腹痛」「じんましん」など)が出やすい傾向にあります。
⑯ 細かいことに気がついたり、些細な刺激にも敏感に反応したり、過剰に刺激や情報を受け止めたりするため、学校での環境や人間関係から強い「ストレス」を感じてしまい、不適応を起こしやすく、 また、人の些細な言葉や態度に傷つきやすく、小さな出来事でも「トラウマ」となりやすいところがあります。
これらの特徴への認識が、HSCに関わる大人の人たちに共有され、慣れるまでのそれぞれに合ったやり方やペースが尊重されると安心です。
しかしそうでない場合、『どうして自分にはできないのだろう』、『どうして自分はほかの子と違うのだろう』という思いが強まって、「自己否定感」や「劣等感」を抱えやすく、さらには「トラウマ(心の傷)」まで抱えてしまっていることが往々にしてあります。
実際にHSCにとっては、学校生活や学校環境は過酷になっていることが多いですから、そのような場合は、学校以外の選択肢を準備して、HSCの気質・特性を活かす道を時間をかけて子どもさんと共に探していくことがとても大切だと思っています。
「義務教育」は、子どもが学校に行く義務ではない
「義務教育」という言葉からは、「子どもが学校に行く義務」というふうに解釈してしまいそうになりがちですが、「義務教育」の『義務』とは、子どもが学校に行かなければならない義務ではありません。
「義務教育の義務とは、子どもの学ぶ権利を保障するおとなの側の義務の意味であって、子どもが学校に行く義務ではなく、親の就学義務も、子どもの学ぶ権利を親として援助する義務であり、登校を強制することが子どもの心を傷つけるような場合に、むりやり学校へ行かせる義務ではない。子どもの学ぶ権利は、学ぶ場と学ぶ方法を選択する自由を含んでいる(『子どもは家庭でじゅうぶん育つ』東京シューレ著 / 東京シューレ出版 P47,P51より引用)」ということなのです。
気質が「社会性」に合っていない
社会は多数派の人の在り方を基準に作られています。
そして世の中の多くの人たちは、基本的に「社会性」を基準として生きています。
「社会性」とは、集団をつくり他人と関わって生活しようとする性質や傾向を持つ、外向性・社交性に価値を求める性質や傾向を持つ、ということです。(個人的には、そこに上下の関係が必ず存在するということを付け加えたい)
世の中全体では、外向型を理想とする人たちのほうが多数で、私たちはその外向型の人間を理想とする価値観の中で当たり前のように生活しているのです。
アーロン博士によると、全体の15~20%がHSC・HSPに該当すると言われていますが、その中の結構な割合のHSC・HSPの子や人たちが、「社会性」を示すような、集団や組織をつくり他人と関わって生活しようとする本能的性質・傾向を持つ人間ではなく、上下が無く対等で安心できる特定の人との関係において、共感や共有を重視するといったより深い親密性や温かい心の交流を求め、その関係性の中から存在意義を見出そうとする、本能的性質・傾向を持っていると私は考えています。
(ただし、外向型の人間を理想とする社会の中に適応しているため、HSC・HSPの中にも外向型を装っていたり、自分は外向型だと信じきっている子や人も一定数存在するようです)
そのため、外向性・社交性や、集団や組織をつくり他人と関わろうとすることに価値を置く「社会性」に対して、ストレス反応(落ち着きがなくなる、動悸や窒息感などの症状が出るなど)が起きやすかったり、不安感や憂うつ感、過度の対人緊張などの症状が出やすく、*敏感性が高ければ高いほど、その傾向が強くなると言えます。
*敏感性の高さの目安
敏感性の高さの目安として参考になるのではないかと思うのが、デンマークの心理療法家であるイルセ・サン氏の著書『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の中のP2-5に記載されている『HSPチェックリスト』のグループAです。あくまでも私の直感ですが、このグループAの点数の合計が100点を超える方は、敏感性が極めて高いと思われます。この点数は、HSPに対する理解が深まるほど、HSPを肯定的に受け止めるほど、UPします。また、現在「社会性」の中に身を置き、外向型を装いながら生きておられる方は、点数が低く出やすい傾向にあります。
現行の医療、例えば、症状を薬で抑える薬物療法や、思考で認知を変えることを目的とした認知行動療法などは、社会に戻すことや、社会性の中で生きることを前提とした治療法であって、HSC・HSPの中でもより敏感性が高い子や人ほど、ご本人が満足するような成果は得られにくいと思います。
それは、気質が社会性に合っていないからであって、身を置いている環境や関係性から離れるという選択肢がない中で、自分を誤魔化したり、ポジティブな言葉やイメージ思考で言い聞かせたり、自分の感情や考え方をコントロールしようとすることに、心が納得していないからなのではないか、と考えるのです。
ただし、過去にストレスやトラウマを抱え、その時のストレスやトラウマに関連した場面や人が重なって、症状が起こっているケースも往々にして見られるため、その場合は、トラウマ回復のためのケアを施す必要があります。
HSC・HSPは、自分の気質に合った環境の中で花開く
私は、本来HSC・HSPの子や人たちは、自分のペースで「自発的」に「主体性」をもって自分らしく生きることに生きがいを感じる子や人たちであり、
そして、
本来HSC・HSPの気質は、人からコントロールされたり、やらされたり、押しつけられたりするなど、その子・人の独自性が阻まれることを強烈に嫌がるほどの「強い個性」であると捉えています。
それは別の視点から見ると、天から与えられた資質(天賦)を完全な姿へと発展させようとする力が強いということでもあるのですが、生まれ持った独自の気質が、その子の個性として花開くかどうかは、その子の生育環境の影響が特に大きいと考えるのです。
子どもの気質に合わせた子育て
時代は変わり、家族の在り方や環境、子育ての仕方も、私の子どもの頃とはだいぶ違いが出てきています。それに伴って、前の時代の「当たり前」のことで、だんだん通用しなくなっているものが出てきている、ということも事実です。
「当たり前」を「当たり前」と思い続けて、それに合わせようとしたり、それを守ろうとしたりすることで、いち早く生きづらさを感じてしまうのも、敏感な気質を持った子どもさんなのです。
だからこそ、学ぶ場や学ぶ方法、働く場や働く方法に変革が必要です。
一部の人の中には、既存の考えに縛られずに、時代の流れをいち早く読み取り、ITを取り入れながら「自分の足で歩き、自分で行き先を決める生き方」をすでに確立されているなど、先見の明に優れた方もいらっしゃるようです。
その意味で、子どもさんが自発的な意志やペースで、子どもさんの身の丈(気質)に合った方法や環境を選択していくことが大切だと思われます。
そしてそのような環境を、親御さんが確信を持って提供できることこそが、子どもさんの個性や感受性(感性)を花開かせる土台だと考えています。
コミュニティ“HSC子育てラボ”について
HSCの気質が妨げられないような子育てには、世間(社会)の常識の枠に当てはまらない選択や判断が必要になる場面が多くなることが予測されます。
ある時は、世間や目上の人の期待や理想を裏切るように思えて、自分にはとてもできないと怖くなるかもしれません。
しかし、子どもさん側の気持ちに寄り添った正確な情報や知識を得ながら、親御さんが支えられ、励まされ、安心や助言を共有できるような場・つながりがあれば、子育てに安定がもたらされていくものと思われます。
HSCのことが書かれた書籍はまだまだ少ないようですし、HSCに対する世間の理解もまだまだと思います。
HSCについてもっと知ってもらいたいと思い、『HSC子育てラボ』というサイトを立ち上げました。
参考文献(出版年度順)
『子どもは家庭でじゅうぶん育つ―不登校、ホームエデュケーションと出会う』東京シューレ/著 東京シューレ出版 2006
『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』エレイン・N・アーロン/著、冨田香里/訳 SB文庫 2008
『ひといちばい敏感な子』エレイン・N・アーロン/著、明橋大二/訳 一万年堂出版 2015
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』 イルセ・サン/著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016
『子どもの敏感さに困ったら読む本 : 児童精神科医が教えるHSCとの関わり方』長沼 睦雄/著 誠文堂新光社 2017